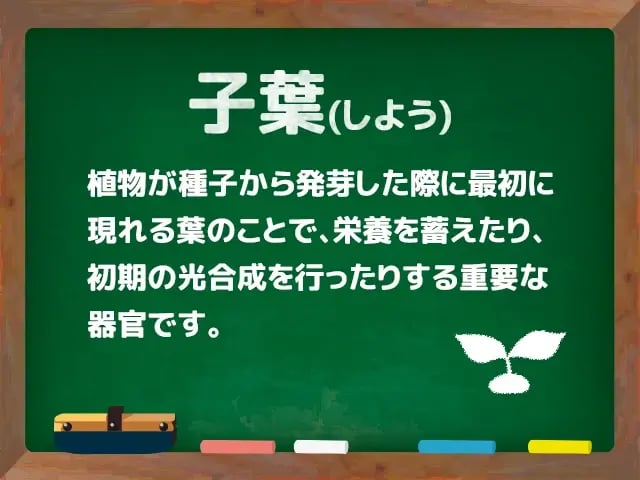
子葉(しよう)とは、植物が発芽した際に最初に展開する葉のことであり、植物の成長初期において非常に重要な役割を果たします。
子葉は、種子の中であらかじめ形成されている葉で、発芽と同時に地上に姿を現します。これにより植物は、種子に蓄えられていた栄養を利用して本葉の形成へと進むためのエネルギーを得ることができます。
単子葉植物と双子葉植物では子葉の数が異なり、前者では1枚、後者では2枚の子葉が見られます。 観察・分類の際にも、植物の分類を識別する重要な手がかりになります。
同意語としては「初生葉(しょせいよう)」があります。
子葉の概要
子葉は、植物の成長過程において最も早く出現する器官で、発芽後のごく初期に機能します。子葉には主に次のような特徴があります。
- 発芽直後に現れる:発芽の際、最初に地上に出る葉が子葉です。
- 栄養の供給源:種子に蓄積されていた養分を含み、植物の初期成長を支えます。
- 分類の手がかり:子葉の枚数で植物が単子葉類か双子葉類かを分類できます。
子葉の詳細説明
植物には単子葉類(たんしようるい)と双子葉類(そうしようるい)の2つの大きな分類があります。 これらは、子葉の数によって分けられます。
- 単子葉類:子葉が1枚のみ。例としては、イネやトウモロコシ、ユリなどが挙げられます。
- 双子葉類:子葉が2枚。アサガオ、ホウセンカ、インゲンマメなどが該当します。
子葉は形や大きさが作物ごとに異なり、発芽直後に本葉とは異なる独自の形状をしていることが多いです。
例えば、ミニトマトやきゅうりの子葉は丸みがあり、本葉が出るまでの間、光合成を助ける役割を果たします。
子葉の役割
- 栄養供給:子葉は、種子の中に蓄えられたでんぷんや脂肪を利用し、発芽後の若い植物に栄養を与えます。
- 光合成の開始:子葉は初期段階から光合成を行い、外部からのエネルギーを取り込んで成長を助けます。
- 分類の目印:農業教育や理科の観察授業では、子葉の数や形状で植物の分類を学びます。
子葉に関する課題と対策
- 課題1:子葉の発育不良発芽条件が悪いと、子葉が小さく奇形となることがあります。土壌の水分や温度が不足していることが原因です。
対策:播種後の適切な潅水(かんすい)と温度管理を行い、安定した発芽環境を整えることが重要です。
課題2:害虫や病気の影響子葉は柔らかく、アブラムシやハモグリバエなどの害虫に狙われやすい部位です。
対策:予防的な防虫ネットの使用や、有機農薬・低毒性農薬を活用することで被害を軽減できます。
課題3:光不足による徒長(とちょう)発芽後に日照が不足すると、子葉が小さく、茎だけが無駄に伸びてしまう現象が起こります。対策:適切な日照量を確保するため、屋外での育苗や育苗用LEDの使用が推奨されます。








